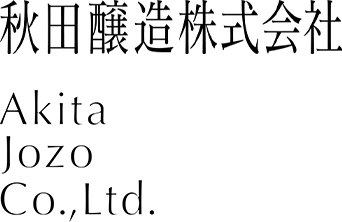新政酒造の佐藤祐輔さんは「ゆきの美人」について「もともと僕が日本酒でやりたかったこと、徒歩5分のすぐ近くで先にやられてたっていう感じ」と話します。「いい酒をつくる」ためにさまざまな伝統に新たな視点を加えた二人。一方で、新政酒造と秋田醸造の「6号酵母」を巡る知られざるファミリーヒストリーも浮かび上がり……。前/後編のうちの後編です。
あのとき、タンクを捨てた
佐藤:小林さんのところは、当初はね、桶売り*1を主にやっていて、桶売りをやめると決めたときには、売り先もほぼ一社だったから、廃業しようか悩まれたこともあったんじゃないですか。
*1)桶売り:酒蔵同士で酒を取引すること。主に大手酒蔵が小規模の酒蔵で造られた酒を買い、自社の商品として販売する。

小林:そうだよ、やめようと思ったこともあった。
佐藤:だけど、やっぱり家業だから続けたいという思いで、一旦は収入をマンション経営にシフトしながらも1階に醸造所をつくられた。あれ、全部ご自分で設計されたんですよね、弟さんが建築家だから。
やっぱりすごいんですよ、あの醸造所。いまだにずっと当時のまま使っていらっしゃるでしょ。あれ、設計が良かったんでしょうね。今になって、変えたいところなんてありますか?
小林:うーん、狭い(笑)。
佐藤:狭いぐらい、別にねぇ。やはり、初めの頃から小林さんの酒づくりって、かなり完成されていたんじゃないかなという印象を僕は持っています。
小林:でもうち、今の蔵を建てたときに新品の貯蔵用タンク結構買ったんだけど、それを思い切って捨てることができたのは、祐輔のおかげなんだよ。
佐藤:そうなんですか?
小林:新政酒造にはね、当時うちのタンクよりもとんでもなくデカい貯蔵用タンクがいっぱいあったの。それをさ、祐輔が「もうパック酒なんか造るのやめる」って言って、オレより先にバンバン捨てたんだよね。それを見てオレも「もう使う予定がないなら新品のタンクでもいらないな」と思ってさ。オレ、まだ1回も酒入れてないタンクを捨てたんだよ。
佐藤:ああ、そんなこともありましたね(笑)。いいものを作るっていうことにぐーっとシフトしたタイミングが近かったんですよね。 でも、それも遡ってみると、やっぱり小林さんが、タンクでお酒を蓄えていると品質が悪くなるから瓶で貯蔵しなきゃダメだっていうことを早い段階でおっしゃっていたからですよ。
小林:そう、酒の品質管理にはすぐ瓶詰めして一升瓶で取っておくのが酒質には一番いい。でも瓶貯蔵は効率が悪いし、置いておく場所も取るからというので、秋田県内のどの蔵でもタンクで貯蔵していた時代もあったんだよな。

小林:瓶貯蔵のほうが絶対いいということは醸造試験場の先生たちも言っていて、秋田県内の蔵元に「瓶貯蔵を!」っておっしゃっていたけど、現実に理論に忠実にやっているのはなんだかんだいって秋田ではNEXT5とほんの数蔵だけじゃないかな。

佐藤:そうそう、僕なんてね、もう言われたとおり忠実にやっているだけですよ(笑)。元ネタはだいたい小林さんからですね。そういえば、当時は、秋田県酒造組合の技術研究委員会のトップを小林さんがつとめてらっしゃいましたよね。
小林:そうだね、うん。
佐藤:当時いい酵母もいくつか発見されていたじゃないですか。秋田酵母No.12とNo.15でしたね。山本さんの「ピュアブラック」は素晴らしい酒ですが、秋田酵母No.12じゃないとあの味は出せないでしょうね。
何を誰に対して作るのか。それがはっきりしていないと、いくらいいものを作ったところで評価はされないって言ってくれたのも小林さんでした。僕は秋田に帰ってきたときに小林さんにそれを言ってもらったから、今があるんだと思います。
小林:それはさ、「ゆきの美人」だってその頃あまり売れてなかったからだよ。「だからこの市場を目指すしかないよね」っていう話は当時、祐輔ともしたのかもしれないよね。
羨ましかったよね。県外の成功している蔵がさ。

佐藤:そうなんですよ。秋田は当時、そういう成功した蔵ってなかったんです。
「クラシカルなスタイル」へ導かれた二蔵のファミリーヒストリー
佐藤:味の面でもね、非常に影響を受けたというか、もともと僕が日本酒でやりたかったこと、先にやられていたっていう感じがあるんです。

佐藤:僕は「磯自慢」(磯自慢酒造)ってお酒を飲んで、すごくおいしいと思ったのが日本酒に目覚めるきっかけだったんです。すっきり爽やかで雑味がない、透明感があって、食べ物に合う酒。すごく洗練されているんですが、当時、それはいわゆる「最先端の酒」ではなく、ちょっとクラシカルなスタイルだったんですね。
当時は—–まあ今でもなんですが、香りが華やかで甘くて濃厚なお酒がもてはやされていましたが、僕は地酒のちょっと古いスタイルの味の形から日本酒が好きになったんですよね。
そういうクラシカルなスタイルのもので、洗練された高級酒っていうのは、市場にあんまりなかった。当時は「磯自慢」のほかに「醸し人九平次」(萬乗醸造)とか……。
小林:「飛露喜」もそうだな、あれはちょっとモダンだけど。
佐藤:そう、香りが控え目で、フレッシュな味わいの酒っていうのが僕は大好きなんだけど、当時も今も地酒の高級酒の市場では少数派です。そういう酒はどうやったらできるのかというと、あえて古い酵母を使うからなんですね。新政酒造は6号酵母の発祥蔵なので、僕は秋田に帰ったらそういう酒づくりをしようと思っていたら、徒歩5分のすぐ近くにすでにそういう酒づくりをしている人がいたんです。
小林:いひひ(笑)。
佐藤:小林さんが香り系の日本酒の方向に行かなかったのはなぜなんですか。華やか濃醇、甘口タイプじゃなくて、初めからすっきり爽やかなタイプだったのはなぜなんです?
小林:実は最初の2年ぐらい香り系の酵母も使っていたんだよ。まずその仕込みで何本か失敗したっていうのが一つ。それからオレがまだどんな酒を作ろうかって迷っていたところに、知り合いの腕利きの杜氏がその当時最新の香り系酵母で仕込んだ、出品酒とまったく同じ貴重なお酒を送ってくれたの。
佐藤:うん。
小林:それを飲んだらさ、なぜかおいしくなかったの。
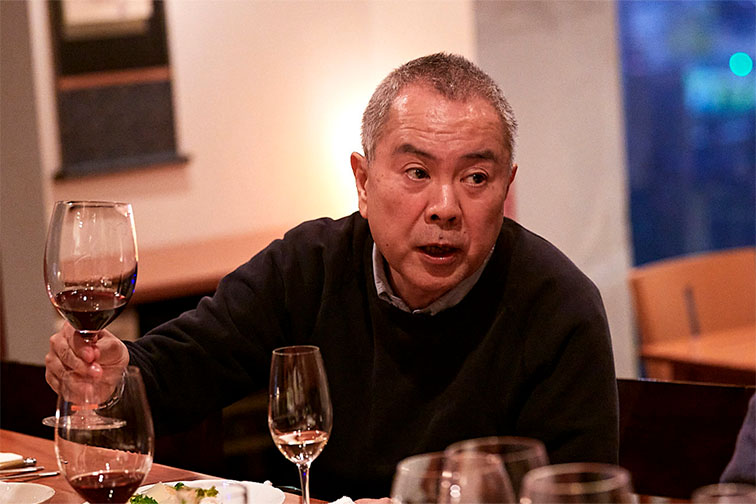
小林:で、「このおいしくなさってなんなの」って理由がわからなくて、 いろんな先生に、「これおいしくないんですけど、なぜなんですか」って聞いて回ったんだけど、みんなわからなくて。
それが華やかな香りのもとであるカプロン酸エチルがちょっと崩れて出るカプロン酸っていう成分の匂い*2だったのよ。それがわかるのに2年かかったけど。
*2)2大吟醸香の一つであるカプロン酸エチルは華やかな香りで熟したリンゴのような香りと言われる。一方、カプロン酸は脂肪酸で汗臭にも例えられる。

佐藤:そうですね。当時は、香り系酵母のデメリットはあまり知られていませんでしたからね。
小林:今はその酵母を使ってうまく作っている蔵もいっぱいあるけど、オレはもうそっちじゃないな、もうこの香り系の酵母はやめようって思ったの。それで古い酵母を使うことにしたんだ。
佐藤:古い酵母としては、小林さんは6号酵母も積極的にお使いになられますよね。この理由ですが、造り酒屋同士として、小林さんの秋田醸造は、新政酒造とは関わりがあるじゃないですか。小林さんのおじいさんがうちの曾祖父の元で杜氏をやっておられましたよね。
小林:そうだね。祐輔のひいじいさんは佐藤卯三郎さんといって、大阪高等工業学校(現在の大阪大学工学部)在籍時からすごく優秀な方で、のちに五代目卯兵衛となる人なんだけど。ニッカウヰスキーの創業者竹鶴政孝氏と同窓生で「西の竹鶴、東の卯兵衛」といわれたほど有名な蔵元だったのね。うちの祖父はその卯兵衛さんのもとで杜氏をやっていてね。
佐藤:そう、小林さんのおじいさんは仕事ができすぎて、満州に行って酒づくりをやらされたりね。大変だったようですね。
小林さんのおじいさんが新政酒造で杜氏をやっていたときに発見されたのが、うちが発祥蔵である「6号酵母」です。
だからきっとそういう流れもあって、クラシックな酵母にどこかノスタルジーを感じていらっしゃるのかなと、僕はなんとなく想像したところもあったんですけどね。

佐藤:やっぱり昔の酵母でつくったほうが、すっきり爽やかなのにしっかり酸が出るんですよね。
小林:こうバキッと。
佐藤:そういうメリハリのある爽やかな酸とちょっと控えめな甘さとか、そういったものが、クラシックな酵母で酒づくりをする際の重要なポイントなんだけど、ごく初期から「ゆきの美人」はそこをうまくクリアしていると思いました。こんな近くで僕の好きなスタイルのお酒を作って、地酒の世界で戦っている先輩がいるんだから、これはとてもありがたいことだと思いましたね。
それはやっぱり小林さんがいろんなお酒飲んでいらして、国際的な感覚だったからでしょうね。そういう方のつくる酒には、きっと地酒の未来があるはずなんです。

佐藤:そういうわけで、僕は小林さんに多くを学ばせていただきました。当時、新政酒造はひどい赤字続きで倒産しかけていたんです。でも、小林さんのおかげで、地酒業界で生き残るのもあながち不可能ではないと思うようになったんですね。
前編はこちら